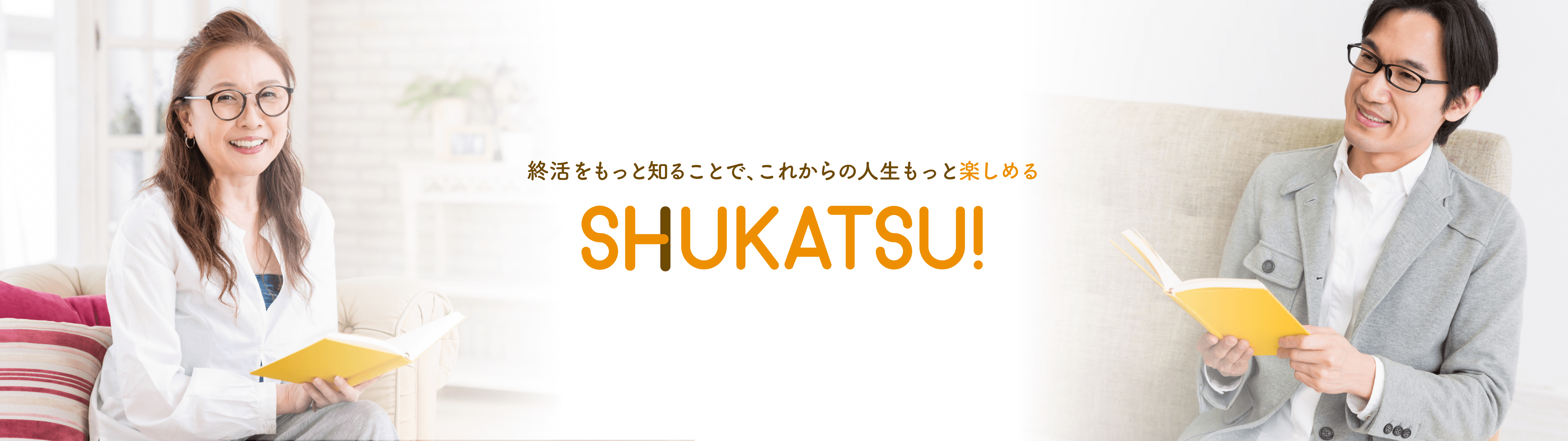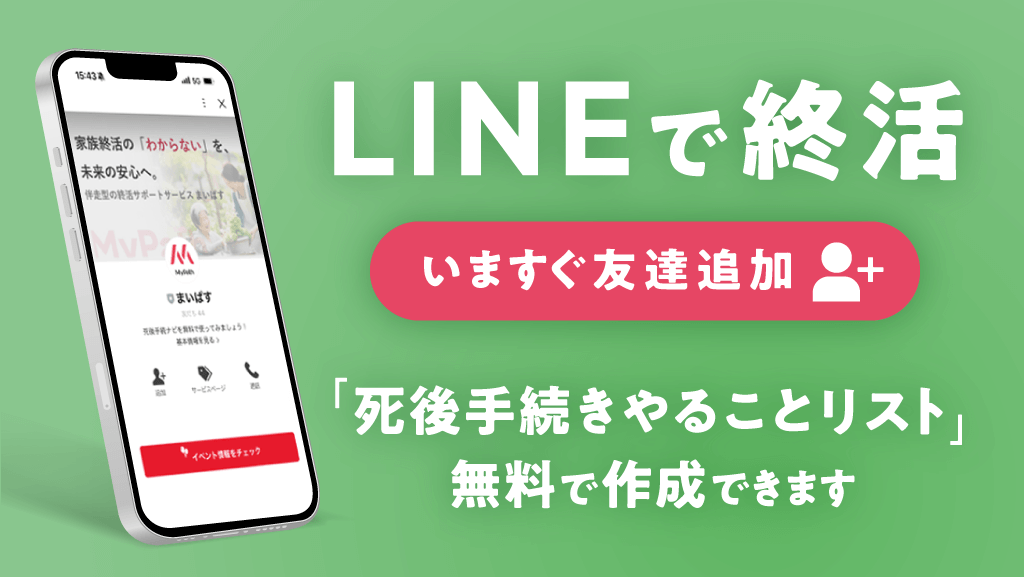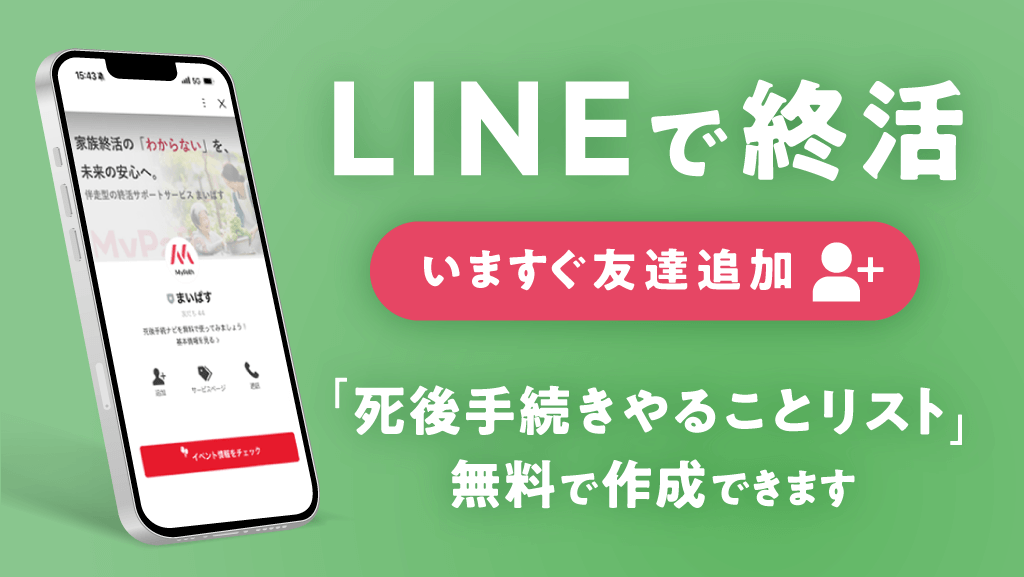1級ファイナンシャル・プランニング技能士が伝える「ふるさと納税」の制度について、更にふるさと納税を上手に活用し「お得制度」のノウハウを簡単に説明します。
近年、ふるさと納税を獲得するための、自治体間の競争が激化しています。自治体からしたら、その町のPRになりますし、財源を手にする機会となるからです。行き過ぎた自治体が処分されることもあるなど、何かと話題のふるさと納税を改めて簡単に解説していきます。
ふるさと納税とは?
まず、ふるさと納税は自治体への寄付金です。
私自信が地方議員であるため、ふるさと納税の本来的な意味、ふるさとや地域を応援したいといった理由で寄附していただきたいのは山々なのですが、寄附をする側からすれば、よりお得に制度を使いたいと思うのも当然なので今回はFPとして解説します。

ふるさと納税はいつ開始してもOKですが2022年に寄附をしていないと、2023年の住民税に反映されません。なので2022年の期限としては、12月31日までということです。
これはポータルサイト等で申し込みをした日で判断するのではなく、自治体に「お金が届いた日 (支払う側の個人からしたら決済された日) 」になります。後日、郵送されてくる受領証明書の日付が寄附日となるので、年内ぎりぎりの申し込みの場合は支払い方法に注意が必要です。
ふるさと納税を節税と思っている人も多いですが、節税にはなりません。むしろ節約という表現が合っています。
例えば…

自治体による返戻商品は、寄付金の30%以内というルールがありますので、2,000円の自己負担の場合は総額20,000円の寄付金(ふるさと納税)となり、その30%に当たる6,000円分の返戻品がもらえます。
もし、ふるさと納税をしていなかったとしても、どちらにしても支払うべき税金ということになります。どうせ払わなければならないお金なら、ふるさと納税をした方がお得なので、人気になっています。
ここら辺の仕組みは、詳細に説明するとかなり複雑ですが、2,000円の自己負担金を支払って、返戻商品を買っていると思っていただけたらおおむね合っています。自治体による返戻商品は、寄付金の30%以内というルールがありますので、2,000円を寄付した場合、6,000円分の返戻品がもらえます。
18,000円はふるさと納税をしようとしまいと支払っていた税金になります。
2,000円は控除の対象とならず、自己負担金となりますので このケースでは2,000円を支払って、6,000円の商品を貰える、だからお得だ。ということになります。寄付金が多ければ、2,000円の自己負担部分を除く返戻商品の金額が大きくなりますが、寄付金には上限額があります。上限額は個人の所得により異なりますが、「ふるさと納税 上限額」で調べると いくつかシュミレーションサイトがありますので実際に自分の上限額を把握した上でふるさと納税をした方が良いでしょう。

さらにお得に活用するためのポイント!
2,000円という自己負担を払って、2,000円以上の商品を貰えるわけですが、より節約をしたいと言う人は普段日常的に使っているものを返戻商品として貰うことをオススメします。
例えば、お米や野菜などです。
こうすることによって、日常的な生活費が少なくなりますので、結果として節約に繋がります。また、楽天やPayPayなどを活用してふるさと納税をすれば、ポイント還元もありさらにお得に利用できるためオススメです。
ふるさと納税をする場合、確定申告しなければなりませんが給与所得者であるサラリーマンの場合、ワンストップ特例制度といって年末調整で完結できる方法もありますので、活用してみましょう。
専業主婦・主夫の場合は、元々税金を納めてないので、配偶者がふるさと納税をすることになります。
冒頭にお伝えしたように、各自治体が寄付金の獲得のために様々な取組を行っています。ふるさと納税のポータルサイトを眺めているだけでも、いろいろな商品があり楽しくなります。
ぜひ、そこから日本の各自治体や、その地域で働き商品を作っている人、また自分の納めている税にも関心を持っていただきたいと思います。

山口市議会議員(政党 無所属)
1級ファイナンシャル・プランニング技能士
日本FP協会認定 CFP®︎
株式会社Comternal 顧問
山口県山口市出身。元JA山口職員(金融部門営業)。山口市から若者が流出するのを防ぐため、同じく若い人間として思いを代弁し、政策に繋げるべく山口市議会議員に立候補。